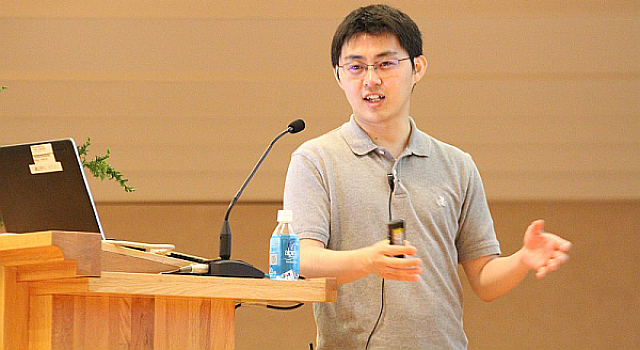定期的にメディアのスポットが当たるも、なかなか本質的な理解を得がたい「女性の貧困」の問題。
そんな中、その問題へ「女性野宿者」という視点から切り込む研究者に、立命館大学准教授・丸山里美さんがいらっしゃいます。
学生時代から京都・大阪・東京の三地域をフィールドとし、研究者として、時に支援者として現場に寄り添ってこられた丸山さん。「野宿者問題」という良くも悪くも男性が中心となりやすい世界に、フィールドワークを主体とする女性研究者として関わってこられている希有な存在です。
何故「女性野宿者」をテーマに選び、その研究から何が見えるのでしょうか?
今回は、ひとりの研究者が出来上がっていく過程での迷いや葛藤、現代の「女性の貧困」を読み解く上で従来の切り口が見落としている問題など、じっくりお伺いしました。
1976年生まれ。京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得認定退学。博士(文学)。現在、立命館大学産業社会学部准教授。共著に『フェニミズムと社会福祉政策』(ミネルヴァ書房 2012)。『ホームレス・スタディーズ』(ミネルヴァ書房 2010)。『女性ホームレスとして生きる──貧困と排除の社会学』(世界思想社 2013)で第33回山川菊栄賞受賞・第3回福祉社会学会学術賞・第5回日本都市社会学会若手奨励賞・第24回橋本峰雄賞を受賞。
釜ヶ崎との出会い
── いつもこのインタビューは「あなたは何者ですか?」という質問から初めているんです。丸山さんにも是非お伺いしたいのですが。
丸山:うーん、研究者のなりそこない(笑)。研究者としてはすごく中途半端だな、と思っています。フィールドに入って支援の現場に関わり、支援者のふりをしながら、でも支援者ではなく研究にウェイトをおいている自分、という状態をすごくずるいな、と。ずっと後ろめたさを感じていました。
── いつ頃から社会の問題に関心をもっていたのですか?
丸山:高校時代からバンド活動をやっていて、好きな音楽を入り口にして黒人差別などの社会問題に関心を持ったのがきっかけです。それで高校生の時進路を選ぶ段階で、社会のことを考えたい、それだったら社会学が一番近いのかな、と思い進学しました。ただ、この時は貧困問題ももちろん、具体的にこの問題を研究したいということは一切なかったですね。
── それがどのようなきっかけで野宿者問題に関わるようになったのですか?
丸山:京大には吉田寮という学生寮があるんですけれども、その寮では毎年釜ヶ崎の越冬活動(※野宿者の方が路上で冬を越すための支援活動)などに参加する文化があるんです。それで「釜ヶ崎にいこう」というツアー勧誘のビラが貼ってあって。知り合いがそれに関わっていたこともあって、じゃあ、と参加したのが最初です。
そうしたらすごく面白くて。1999年の当時は釜ヶ崎でもホームレスの方が特に多い時期で、路上にもたくさん人が寝てるし、そこら辺でお酒も呑んでいるし、やたらと人が話し掛けてくるしで、ちょうどこの頃バックパッカーとして行き始めた「アジアの国々」に来ているようだと思ったんです。半日ばかりのツアーだったのですが、来る前までの「悲惨な街」というイメージとはうってかわって「活気があって楽しい街」という印象を抱いて帰りました。
帰ってからしばらくは関わらなかったのですが、その後三回生になった時に卒論はフィールドワークをして書きたいな、と思ったんですね。それもちょっとやるのではなくて、二年くらいかけてきちんとやりたいな、と思っていて。じゃあどこをフィールドにしようか、と考えた時に、印象深かった釜ヶ崎に決めたんです。ただ、その当時の研究テーマは「ボランティア」でした。
── 何故「ボランティア」をテーマにしようと持ったのですか?
丸山:バックパッカーとしてインドに旅行した折、最終日にカルカッタへたどり着いたんですが、そこにマザーテレサの「死を待つ人々の家」という一種のホスピスがあるんです。明日死ぬかもしれない人たちがだだっ広い空間に布を敷いて寝ていて、世界中から集まったたくさんのボランティアが食事を運んだりシモの世話をしたりしている空間で、私も偶然出会った日本人旅行者に誘われて半日だけボランティアをしたんです。これがいろんな意味で衝撃的な体験でした。
実は私はそれまでボランティアというものにもほとんど関心がなかったんです。私がちょうど高校三年生だった95年に阪神大震災を契機にしたボランティアブームが起こったのを目の当たりにしたんですけれども、自分は受験生でかかわる時間もなくて、大学生になっても人のために何かをしたいという思いは特にありませんでした。ただ「ボランティアはすごくいいことをしている」というイメージはあったんですね。
けれど「死を待つ人々の家」で世界中から集まったボランティアの人々を見聞していると、自分の持っていたボランティアのイメージとだいぶ違う現実がそこにはありました。ボランティアしている目的が「好きになったボランティア仲間の女の子に近づきたいから」と公言する人がいたり、観光半分で来るボランティアの人を満足させるために常勤スタッフがわざわざ不必要な仕事を作ってやってもらったり。
この経験から「ボランティアはいいことをしている」という、そんな単純なものではないな、と思ったんです。それで「じゃあボランティアってなんだろう?」と改めて考え、卒論のテーマに選びました。
「ジェンダーの問題」への気づき
── 釜ヶ崎ではどのような活動をされていたのですか?
丸山:主に炊き出しの手伝いですね。野菜を切ったり、配食したり。当時は2000食くらい出していたので、朝5時から準備を始めて配食するのが12時という大変な状況でした。ただ、すごく面白かったですね。いろいろな人がボランティアに来ていて、日雇労働者や、自分のような学生もいたし、教会のシスターや普通の主婦の方もいたりで、一緒に作業しながら無駄話をしたりしていました。炊き出しに並んでいるおじさんとも仲良くなって可愛がってもらってもらいました。
── 調査としてはどのような形でおこなっていたのですか?
丸山:特別には何もしていなくて、炊き出しをしながらいろんな人に「なんでボランティアをしているんですか?」と素朴に聞いてまわるくらいでした。そんな生活を三回生の夏から始めて、週一回~二週間に一回の頻度で定期的に通ううちにすごく楽しくなって「こんな生活を続けるためにも研究者になろう。大学院に進学しよう」と決めたんです。ただ、私は本当に試験が苦手で、最初に受けた院の入試に落ちてしまい、1年留年してしまいました。
── ところがトラブルが起こります。
丸山:はい。釜ヶ崎で活動する中でいろいろな出会いがあったのですが、その中でここで暮らす男性にラブレターを貰ったんです。すぐにお断りしたのですが、誤解も重なって、最終的にはストーカーのようになってしまいました。しょっちゅう電話が掛かってきたり、家にまで押しかけられたりして、すぐ道で包丁を持って待ち伏せされているんじゃないかと怯えてすごしていました。
でも、大学院に進学するためには卒業論文は書き上げなければなりませんし、フィールドワークを始めた以上現場との良い関係を維持して、論文もその人たちに読んでもらって調査を終えるというのが正しい道なのだと考えていたので、最後は「会いませんように」と祈りながらむりやり現場に向かっていました。こんなトラブルが自分の身にふりかかって初めて、女性がこのような場に通ったり、そこで暮らしたりすることの困難さを実感したんです。
── ここからジェンダーの問題に注目していったのですね。
丸山:そんなことになるまで私はジェンダーの問題にあまり関心がなかったんですね。だからこそ、釜ヶ崎というおじさんの多い街に平気で通うことが出来たんですけれども。ちょうどその頃「寄せ場交流会」(※年一回、全国の「寄せ場」の関係者が集まり、討論と親睦を目的としたイベント)に参加した時に、他の女性支援者と話す機会があって、同じようなトラブルを抱えている人が他にもいたんです。それでやっと「あ、なんだこれは私だけの問題じゃないのだ」と腑に落ちました。
その時から、関西をベースにしている五名の女性支援者が中心となって「寄せ場交流会」の女性版を一度開催しようと、五回生でほとんど大学にも行かずにその準備や釜ヶ崎での活動に奔走していました。そうして開催時には全国から30人弱の支援者が集まってくれて、メンバーには「女性ネット Saya-Saya」の松本和子さんや、当時新宿で女性野宿者のお茶会をしていた池田幸代さんなどもおり、一泊二日でハラスメントの問題などいろいろなお話が出来ました。
そのときにも、女性支援者の問題とともに、女性野宿者の問題についても話しあったのです。その当時、女性野宿者を扱った研究は不十分でした。だったら自分がジェンダーの問題を、寄せ場やホームレスの切り口から取り上げたいと、大学院での研究テーマを「女性のホームレス」に決めたんです。
「調査の失敗」を乗り越えて
── そうして「女性のホームレス」問題に取り組もうとスタートしたわけですが、最初はどのようなアプローチをされたのですか?
丸山:女性ホームレスの数が少ないことはわかっていたんです。ですから、どこで話を聞いたりアプローチしたりすればよいかが一番苦労したところでした。ともかくまずは話を聞ける女性野宿者を探さないといけないと思ったんですけれど、なかなかすぐには見つからなくて、大阪・釜ヶ崎のまちづくりの活動や、京都の夜回り、東京の団体や施設など、三地域を放浪しました。
そうやっていくつかの支援団体に顔を出し続けていると、少ないながらも女性野宿者や、元女性野宿者と知り合って話をする機会を持つことが出来たんです。ただ、そんな彼女たちに「実は修士論文を書こうと思っているんです。だからお話を聞かせてくれませんか?」とはなかなか言い出せない日々が続きました。
── それは何故でしょうか?
丸山:卒業論文を書く際のフィールドワークで起こったトラブルに関連して「自分はうまく調査が出来なかった」「調査に失敗したんだ」と、ずっと劣等感を抱いていたんです。「そしてそれは調査員の能力の問題である」とも。今になってみると、問題だったのはハラスメントなど別の要因もあったと思えるようになったのですけれども。
ただ、当時はそんなだから「自分なんかの研究のために協力して下さい」とは、なかなか切り出せませんでした。今現在困っている人に、自分の研究のために話を聞かせてもらうという能天気なことをお願いしていいのか、という葛藤もありました。当時出入りしていた京都や東京の支援団体で女性野宿者の方とも知り合うことが出来たし、女性野宿者が集まっているお茶会に参加したり、元女性野宿者が入所している施設でアルバイトが出来ることにもなり深夜バスではるばる通勤したり、機会と繋がりは増え続ける一方、肝心のことは頼めず時間ばかり過ぎていきました。
── どのようなきっかけで話を聞くことができたのですか?
丸山:それはもう、いつかは頼まざるをえなかったので、最後は思い切ってお願いしました。それでもずっと劣等感や葛藤はぬぐえませんでしたけれど。ただ、結果としてお話を聞けた方々にはすごく良くしてもらえて、無事論文の形にまとめることができました。
その後、その論文をベースに『女性ホームレスとして生きる──貧困と排除の社会学』(世界思想社 2013年)という本を出すことが出来ました。博士号をとるまで結局九年掛かり、今のポストにたまたま採用されました。現職にいるのは本当に運だと思っています。始めた当時は自分も貧困だったのですけれど、今は研究者というある程度安定した身分を得て、問題に関わっている。その特権的な立場にいることの後ろめたさと、でもこの立場になってしまった以上、そこでできることを考えていかないといけないという気持ちはありますね。
不可視化された「女性の貧困」
── 「女性の貧困」については様々な形から定期的にメディアに取り上げられている状況ですが、丸山さんから見て、見落とされている点はないでしょうか?
丸山:「女性の貧困」という形でよくメディアで取り上げられるのは、ひとつは「シングルマザー」の貧困。もうひとつが「風俗に流れざるをえない若年女性」の貧困。それと時々「高齢単身女性」の貧困、大きくわけてそれら3つだと思います。もちろんそれらの女性が貧困なのは間違いありません。女性が貧困になる場合、家に男性の稼ぎ手がいない時に、比較的貧困になりやすいと考えられます。これら三つのパターンはまさにその状況ですよね。
貧困の問題を考える時に、今現在は「世帯単位」で貧困かそうではないかを把握されます。そうなると女性は、夫の収入があったり家に住んでいたりすると、その時点では貧困でもないしホームレスでもない。
けれど、家の中に男性がいたとしてもその関係がうまくいっているとは限らないし、男性がお金を持っていたとしてもその妻はお金をもっていないケースもある。DVで困って女性が家を出たいとしても、その女性がパートや専業主婦だったりすると自活するお金はないわけですよね。その状態で出てしまえば貧困やホームレスになってしまうかもしれない。だから家の中に留まらざるを得ない「見えない貧困女性」がいるのではないかと考えています。
女性ホームレスのことを研究していると「何故野宿者の女性が少ないのか?」ということをよく聞かれるんです。ひとつ一番大きな理由をあげるとすれば、「女性ひとりが生きていくという選択が、そもそも出来ない社会だから」ということができます。女性の経済的自立が難しいということ、つまりは女性が単身でやっていく、もしくは離婚してやっていく、そのような選択肢がしづらいくらい女性が差別されている社会なんだ、ということが大きいのだと考えています。
ですから、単純に表面的な経済状態で「女性の貧困」を捉えようとするのは違うのではないか、世帯ではなく個人単位で貧困を捉えること、相談の現場においては金銭的なものだけではない困りごとをすくい上げていくことが必要ではないかと最近は考えています。
── 若者の場合も貧困のため実家から出ることが出来ず、結果として貧困状態が見落とされてきたというデータがありました。同じような状態が女性の場合にもあるということなのですね。今まで上げていただいた問題点を含めて、今後丸山さんが重要だと考え、突き詰めていく必要があると考えてる視点をお教え下さい。
丸山:ふたつあります。ひとつは「女性の貧困」の貧困概念自体をもう少し刷新出来ればと考えています。経済的な問題だけではない部分をもっと視野にいれること、そして世帯単位で貧困を捉えるのではない方法が必要だと感じています。「家から出たいのに出られない女性」について視点を持つことも含めて「そもそも女性の貧困ってなんだろう」と捉え直したい。
もうひとつは社会福祉政策とジェンダーの関わり、その中で特に現場レベルにおいてのジェンダー規範を明らかにしたいと考えています。そもそも社会福祉制度には「望ましい生活とは何か」という社会の規範が埋め込まれており、当然そこには「男性に求められるべき正しい姿」や「女性に求められるべき正しい姿」のようなジェンダー規範も含まれていると考えられます。「売春防止法」のように政策レベルでの明確な女性差別はもちろんですが、そうした政策レベル以外にも、もっと現場レベルで見ていかなければならないのではないかと思います。
というのも、制度・政策と、実際に現場レベルにおいてそれが運用される時のあり方は、必ずしも一致しませんよね。たとえば「生活保護」という制度が持つ理念と、実際にそれがどうやって運用されたり適用されたりするかは、また異なります。そして現場を見てみると、貧困に陥ったその人に影響があるのは、制度の理念だけではなく、「ケースワーカーにこう言われたから」のような運用の末端にいる人間の意識や態度、その地域での運用の慣習だったりするという現実があります。
それはもちろんジェンダー規範も同じで、制度内のジェンダー規範だけでなく現場レベルにおいてのジェンダー規範がどのようなもので、それが当事者にどのような影響を与えているのかを明らかする必要があるし、してきたいと考えています。
とても大きなテーマなので、これはライフワークになるなと思っているのですが。[了]